記事カテゴリ
高血圧の正しい診断とは?
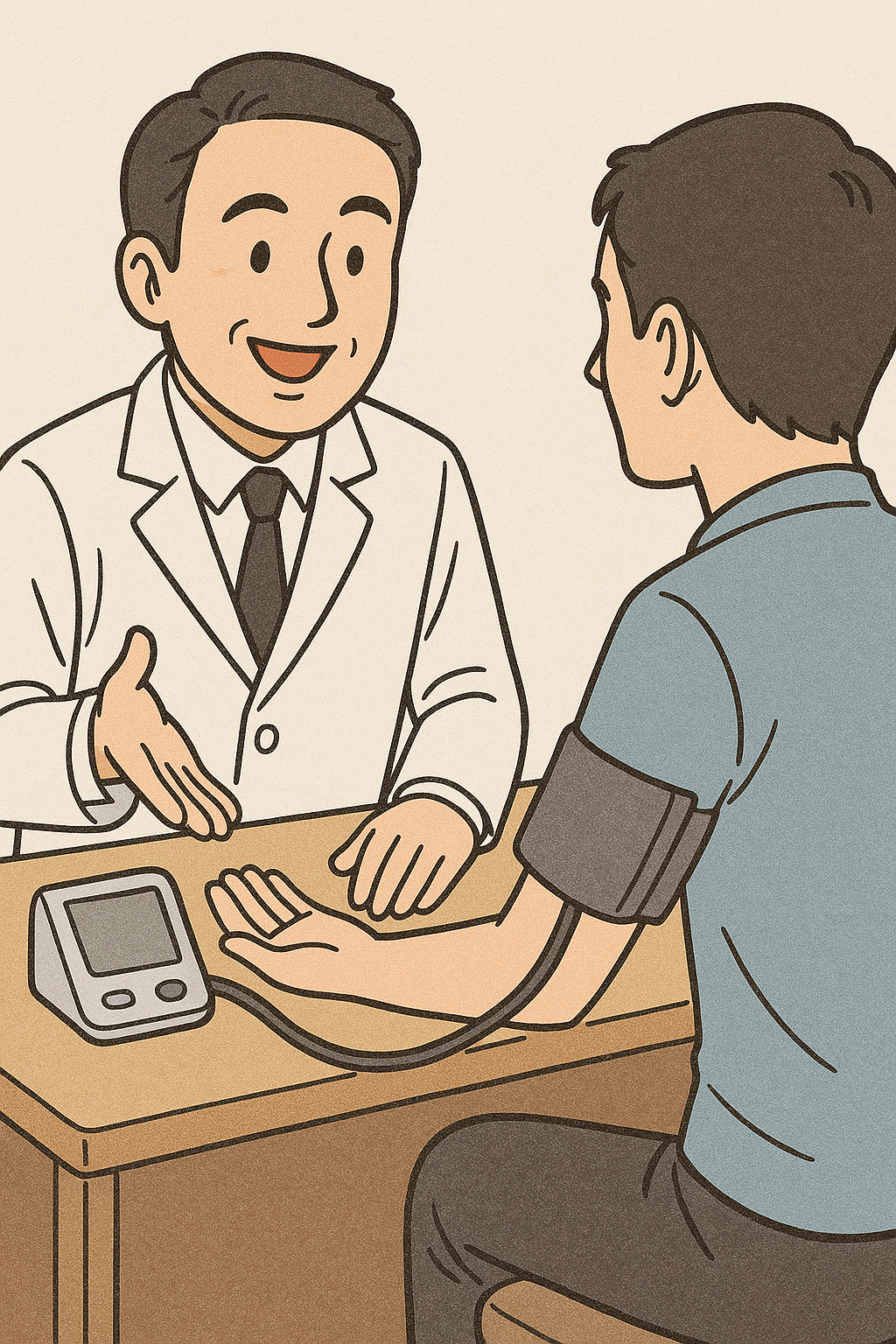
Contents
1. はじめに
高血圧は「サイレントキラー(沈黙の殺し屋)」とも呼ばれるほど、自覚症状がないまま進行し、気づいた時には脳卒中や心臓病といった重大な病気を引き起こす危険があります。ところが、一部で「血圧は年齢+90までなら大丈夫」といった誤った考えが広まっており、そのために治療や生活習慣の改善が遅れてしまうことがあります。ここでは、最新の科学的根拠に基づいた正しい高血圧の診断について概説します。
2. 年をとれば血圧が上がるのは自然なこと ?
「年をとれば血圧が上がるのは自然」だから「血圧は“年齢+90” までは正常範囲だ」と聞いたことがある方もいるかもしれません。しかし、これはだいぶ昔に言われていたことで、現在の医学的根拠に基づくものではありません。
実際、加齢に伴う血圧上昇は自然現象ではありません。南米のヤノマミ族など塩分をほとんど摂らない民族では、加齢に伴う血圧上昇がみられないことが知られています。つまり、加齢に伴う血圧上昇は避けられない現象ではなく、主に塩分の多い食生活や生活習慣 によるものなのです。
3. 高血圧の診断基準は診察室血圧140/90mmHg以上
現在では、日本の久山町研究やNIPPON DATA研究を含む世界中の大規模な研究から「年齢にかかわらず、血圧が高いほど脳卒中や心臓病のリスクが高くなる」ことがはっきりとわかっています。たとえば、40歳でも80歳でも、収縮期血圧(上の血圧)が140mmHgを超えていると病気のリスクが上がるのです。
そのため、日本を含む国際的なガイドラインでは、診察室血圧(医師や看護師が医療環境下で測定した外来血圧や健康診断時の血圧の総称)が、収縮期血圧(上の血圧)140mmHg以上、または拡張期血圧(下の血圧)90mmHg以上の場合を、“高血圧”と定義しているのです。
4. 診断基準は病気を防ぐためにある!
「正常値を低く設定するのは医者や製薬会社が儲けるため」というご意見も耳にしますが、実際には逆で、多くの専門家や公的な国際学会(世界保健機関WHOや日本高血圧学会など)では、人々の健康と命を守るために膨大な研究データをもとに基準を決めています。薬を使うかどうかも、「リスクが高い方にだけ必要に応じて使う」というのが基本です。つまり、高血圧の診断基準は「儲けのため」ではなく、「脳卒中や心筋梗塞を防ぐため」に科学的根拠に基づいて定められたものなのです。
5. 高血圧は認知症のリスク!
加えて、高血圧を放置すると、脳の血管にダメージが蓄積し、脳梗塞や脳出血だけでなく、将来の認知症リスクも高くなることが数多くの研究で示されています。日本の久山町研究でも、中年期に高血圧だった人は、その後の認知症(アルツハイマー病や血管性認知症)のリスクが有意に高いことが明らかになっています。血圧コントロールは、認知症の予防にもつながる「脳を守る治療」であることが国際的に強調されています。
誤った診断基準を信じて「自分はまだ大丈夫」と思い、高血圧を放置することは、将来の脳卒中や心臓病だけでなく、認知症のリスクを高める危険な行為といえます。
6. 家庭血圧を測りましょう!
病院での血圧は緊張の影響を受けやすいため、近年は家庭で測定する血圧(家庭血圧) がより重視されています。家庭血圧による高血圧の診断基準は、“135/85mmHg以上”です。
家庭血圧は日常の状態をより正確に反映し、将来の脳卒中や心臓病の予測にも優れていることが、日本の大迫研究を初めとする多くの研究で明らかになっています。
健康を守るためには、病院での測定だけでなく、ご家庭での定期的な血圧測定が欠かせません。測定を続けることで、自分の血圧の傾向を把握でき、早期に異常を発見できます。まだ家庭血圧測定を始められていない方は、ぜひとも始めることをお勧めします。
測定方法は本協会ホームページに掲載の「血圧手帳」をご参照ください。また、血圧値の記録にも「血圧手帳」を是非ご活用ください。
7. おわりに
高血圧の診断基準は、医師や製薬会社の都合で決められたものではなく、世界中で長年にわたり積み重ねられた科学的な研究によって導き出されたものであり、その目的は「病気を防ぐこと」です。
「年齢が上がれば血圧が高くなるのは当たり前」という誤解にとらわれて放置してしまうと、脳卒中や心臓病だけでなく、認知症のリスクも高まります。正しい基準を知り、生活習慣を整え、毎日の家庭血圧測定を習慣にし、血圧を適切に管理することで、その多くを予防できます。その積み重ねが、自分や家族の健康を守り、将来の安心と健やかな暮らしにつながるのです。

